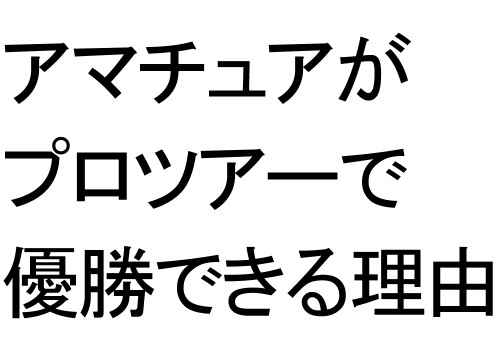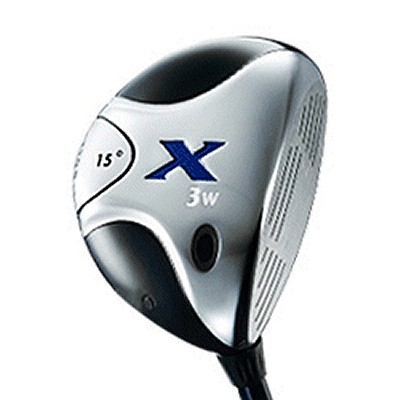ここ数年、アマチュアやプロ1年目の選手がプロツアーで優勝するシーンが珍しくなくなってきました。
若手の活躍は喜ばしいことは確かですが、一方で、中堅・ベテランはどうしているのか?何故、若手が第一線で通用するのか?
そこには、昔とは違う幾つかの理由があります。
プロツアーでのアマチュアの優勝が増えている!
▼プロツアーで優勝したアマチュアゴルファー
| 年度 | ツアー | 選手 |
|---|---|---|
| 1973年 | 女子 | 清元登子 |
| 1980年 | 男子 | 倉本昌弘 |
| 2003年 | 女子 | 宮里藍 |
| 2007年 | 男子 | 石川遼 |
| 2011年 | 男子 | 松山英樹 |
| 2012年 | 女子 | キム・ヒョージュ |
| 2014年 | 女子 | 勝みなみ |
| 2016年 | 女子 | 畑岡奈紗 |
| 2018年 | 女子 | クリスティン・ギルマン |
| 〃 | 男子 | 金谷拓実 |
| 2019年 | 男子 | 中島啓太 |
| 〃 | 女子 | 古江彩佳 |
| 2022年 | 男子 | 蝉川泰果 |
アマチュアゴルファーの優勝というと、宮里藍、石川遼、松山英樹といった辺りを思い浮かべる方も少なくないと思います。
しかし、それも今や昔となりつつあります。
確かに、以前はアマチュアゴルファーが優勝することは珍事でして、宮里藍の時は30年振り、石川遼の時は27年振りでした。ちなみに、その4年後には松山英樹が優勝しています。
転機とも言えるのはそこから約10年後であり、直近の10年とも言えます。
女子では宮里藍の優勝から9年後のキム ヒョージュ、男子では石川遼の優勝から11年後の金谷拓実が優勝し、そこから勝みなみ、畑岡奈紗、クリスティン・ギルマン、古江彩佳、中島啓太、蝉川泰果らを含め、最近の約10年間で8名ものアマチュア優勝者が出ています。
アマチュア・若手が活躍できる3つの理由
目立つのはアマチュアによる優勝だけでなく、特に女子ツアーでプロ1年目や20~22歳ぐらいの新人ゴルファーの優勝です。
象徴的なのは、2022年9月の川崎春花、尾関彩美の優勝です。共にプロ転向1年目の19歳が2週連続で優勝しました。川崎春花に至っては国内メジャーという大舞台を最初に制してしまいました。
そこには、中堅・ベテランのゴルファーから聞こえてくる話から、幾つかの理由が見えてきます。
理由1:ITの普及がもたらすスイングの変化
ゴルフのレッスンと言うと、宮里藍や横峯さくらのように、親が教えるのが一般的だった時代がありました。
そこには我流の練習法があり、身に付いたスイングは独特な選手も少なくありませんでした。
しかし、最近の若手は、どの選手もスイングがとてもきれいです。
今と昔の違いについて、有村智恵プロもは以下のように述べられています。
私が若手の頃は、鏡の前や誰かに見てもらうというアナログな確認方法でした。
今は自分のスイングをスマホで撮ってすぐに見られるようになりましたし、海外の有名選手のスイングを解析した動画が気軽に見られるのも大きいと思います。
*引用:yahoo.co.jp
これはゴルフだけに限らず、野球などでも当てはまる話です。
スマホやタブレットの普及により、映像が身近になりましたし、何より、youtubeで最近であろうが過去であろうが、色々な選手のスイング映像が大量に転がっています。
ビデオで録画してテレビの前で見ていた時代とは、情報量の面で大きくことなるのは言うまでもありません。
理由2:アマチュアの試合日数の変化
プロの試合と言えば、男子は4日、女子は3日が当たり前です。
一方、アマチュアの世界では、以前は2日が多かったところ、最近では日数が増えています。
▼石川遼プロが語るアマチュアの試合日数の変化
4日間で勝つことが男子では求められていて、アマチュアの試合でも4日間が増えてきたのがあるのかな。
メジャーも4日間の試合で勝負をつけるのが世界の基準。(ゴルフは)2日、3日、4日で全然違う。
プロからすると『アマは失うものがないからガンガン行ける』という声もあるが、それが4日間続くことは難しい。うまければ上に行ける、もろければ崩れていく、というのが4日間だと表れる。
*引用:yahoo.co.jp
ゴルフは男子だと4日間の長丁場で、偶然や一発勝負が通用しない世界です。そこがアマチュアにはメンタル面・体力面を含めて壁でもありました。
しかし、石川遼プロの指摘の通り、最近はアマチュアの試合環境をプロ・世界標準に近づけていますので、アマチュアがプロツアーでも普段と同じようにプレーしやすくなっているのは間違いないでしょう。
加えて、男子プロに関しては、大会数が減り続けています。アマチュアのプレー環境が充実しているのと対極的に、プロの活躍の場が縮小していることも、若手の台頭につながっているのかもしれません。
理由3:道具の進化
ゴルフクラブは、メタル、チタン、カーボンといった素材の変化に加え、AIを駆使した設計、パーシモン時代には考えられなかったテクノロジーの採用により、以前とは比べ物にならないぐらい進化しています。
単に飛距離が出るだけでなく、曲がらない、球が上がるといった特徴を持たせることも可能で、それがプロに求められるスイングにも影響しています。
▼有村智恵プロが語る最近のゴルフの攻め方の違い
同世代や先輩の方々と会話すると、『自分たちが若い頃のゴルフは球を操ったり、曲げたりする練習を主にしていた』という話になります。
今は道具の性能が上がって“曲がらないクラブ”になっています。
今は“曲げなきゃいけない場面”というのは、ほとんどなく、とにかくピンの根元に高い球を打つことが、攻め方としては合っていると思います。
*引用:yahoo.co.jp
テーラーメイドのステルスというと、ドライバーのカーボンフェースを思い浮かべる方が多いと思いますが、実はアイアンも革新的なテクノロジーが採用されています。

ヘッドのトゥ側の金属が取り除かれていて、更なる低重心化が図られています。
以前では考えられなかったことが実現されていて、クラブの進化は、今尚、終わりが無く進んでいます。
有村智恵プロが指摘している通り、曲がらない、上がるクラブは簡単に作れますし、その反対に、超低スピンで上がらないクラブ、重心を思い切り浅くして曲がりやすいクラブも簡単に作れます。
フィルミケルソンの長尺・絶壁ロフトのドライバーのように、自分の技術で球を操作するというより、自分に合ったクラブを見出す力の方が重要になってくる時代になっています。
まとめ
アマチュアや若手プロが、プロツアーで活躍できる理由について、取り上げました。
ITの普及、アマチュアの試合日数の変化、道具の進化が主な理由として挙げられますが、更に、トレーニングの手法・マシンの進化により、早くから肉体を作り上げられる点も大きな理由の一つとして挙げられます。
実際、アマチュアがプロ以上に飛ばしているのも、その恩恵があると言えるでしょう。